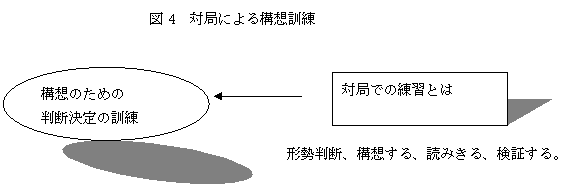囲碁が強くなるには、縦糸と横糸の2つの知識と実践対局として学習が必要です。
- 縦糸とは、
- 大局観や構想における考え方であり、ゲームとしての全局的な動きを生む理論知識
- 横糸とは、
- 布石、死活、攻め合い、寄せなど、ゲームとしての部分的な動きを生む技術知識
のことです。そして、実戦対局とは、この縦糸と横糸との組み合わせの総合練習であり、場面での状況を判断しながら、失敗や成功から学ぶ経験になります。上達には、この3つが絶対条件となります、この中のどれか一つでも欠けると、なかなか「上達できない病」にかかった状態になります。
図1 構想と学習目的
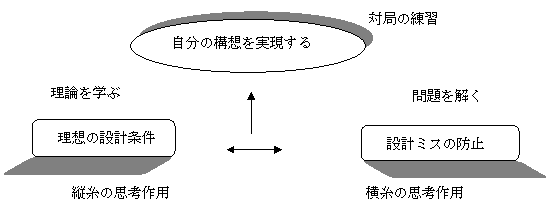
1部分知識は思考道具にしか過ぎない
囲碁は失敗に多いゲームであるため、部分的な死活、布石などの基礎技術がないと、スタートから失敗の連続という事態となり、すぐに勝てない状況になってしいます。つまり「部分的なミスによる、損失の回避」ができないのです。このように、部分的な知識は非常に重要なのですが、部分的な知識は、碁を打つための道具でしかありません。もっと厳密にいうなら、構想のミスや着手ミスを起こさないための知識なのです。そのため構想目的の知識がなかったり、対局経験が極端に少ない場合や、その知識の活用を理解せず、覚えた定石の手順を実戦で打とうとしても、効果がないだけでなく、無理に使用しようすればするほど、今まで勝てていた相手であっても、勝てなくなるという棋力の低下状態が起こります。つまり「定石を覚えて2子弱くなり」という格言がピッタリな状態となるのです。
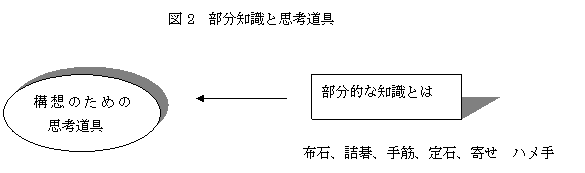
2全局的な知識だけでは、失敗をふせげない
構想としての理論をいくらよく解っていても、また、このようなミスによる損失を取り戻すには、大変苦労するゲームであるため、単純なミスをできるだけしないことまた無くす努力が上達の基本条件になっています。高段になれば、このような部分的な知識不足による失敗はほぼゼロになります。高段での棋力差は、囲碁理論の理解力の差、その経験差が全面的に現れることになります。
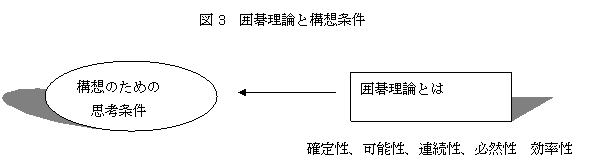
3実戦での連取の失敗から学ぶ知識
実戦対局での失敗は、上達において避けることができない体験といえます。是非勇気をもってチャレンジしてください。この失敗体験での反省によって、「自分の考え方にとらわれの意識がある」ことがわかってきます。この経験を積み重ねることで、正しい考え方と感性のあり方への軌道修正が「他人からの一般知識ではなく、自分内部からの気づきとしてわかる」状態になります。この過程を通じて、本質的で本物の囲碁上達が可能になります。本物か偽物かの違いは、構想として「戦い方」や「石の流れ」、「着手目的の必然度」で客観的に判断できます。つまり構想として正しい目的設定がなされ、その達成方法が自然で無駄のなく、また必然的な石の流れになっているかどうかで判断できるのです。このことをより意識し構想をたてること、さらに学習効果が高まること になるのです。