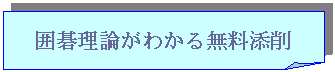
囲碁理論の第一人者が、布石の考えか方を伝授する
こんな体験をしてみませんか。
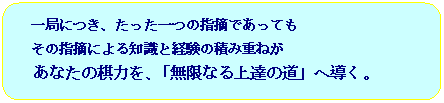
◇
無料の棋譜添削によってわかった
囲碁理論の不足による上達への障壁
1. 戦いの構えを意識していない。
すべての布石は、戦いに構えを基本にして出来上がっています。
どこから戦いが始まるのか。不利な戦いをどのように避けるのか
有利な戦いをどのように展開するのか
2. 黒番の布石が目立って悪い
構想を立てることができないため、黒番での大場選択ができない。
大場や好点の選択に、囲碁理論としての構想がわかっていないため緩手を連発する。
白番の場合には、相手の手に対応するので、緩手であっても問題が少ない。
3. 完全に生きた後も、続けて打つ。
生きた石の周囲は、戦いが終った焼け跡の場所…そこから、すぐの新芽は生まれない。
4. 中央への打ち込みを4線に打つ
「打ち込み」と「はさみ」、「しまり」そして「消し」の概念が混乱している。
辺中央への割り打ちの「打ち込み」で、左右に開ける場合は、必ず3線に打つ。
挟みの基本は4線に打って。相手から攻撃に備える。
ただし、挟みとしまりが一石2鳥の場合は3線に打つ。
消しの基本は5線以上の場合が多い
消しの手は、相手に地を囲わせることを強要する手のこと
5. 星に対して桂馬かかった石に、必ず受ける。
このため、両かかりの定石が打てない
挟む定石が打てない。
特に置碁での布石(4子局以上)では
白番の3手までは、受ける手は打たない。はさむ手を選択する。
受ける手が悪手ではないが、受ける人は、「戦いの構え」ということが学べない。
特に、攻めるテクニックがない級の人は厳禁。構想もなく受けると、その後が緩手のオンパレードに
なっている。このことが、緩手を平気で打つ習慣を作り出すことになる。
6.
分断する手を、最優先で打たない。
5線に一間に飛びだし分断する手より「3線にすべる」、また「2線に這う」手を打ちたがる。