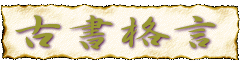|
第一章 序之部
1
その昔、支那古代の皇帝堯・舜は碁を創案し、子息の教育のためにこれを教えたという。ある人がその事に疑いを持ち、堯の子朱、舜の子均は愚者であったと聞いているが、いやしくも聖人とも仰がれる人ならば、教育に当たっては仁義礼智の道を説くはずである。
どうして閑つぶしの道具等を作り、敵を騙す術を教えたりして、その愚を増長させる様な事をするだろうか? そんなはずはあるまい、と言ったという。
2
私はしかし、碁とはそういうものではないと思う。
そもそも碁というものは、その形象からして天の円く地の角に似せて作られており、
黒白の争いには自ずから天地陰陽動静の道理が働いている。
打ち進められた盤面には天上の星の如く秩序整然たるものがあり、
局面の推移には風雲の如く変化の機運に富んでいる。
活きていた石が死ぬという事もあり、全局を通じて変化し流れ行く様は恰も山河が表裡をなして種々な容相を呈するが如くである。そうだとして見れば、人の世の道義や浮き沈みというものも、一つとして碁になぞら得ぬものがあるだろうか。
3
考えて見えるに、名人上手といわれる人は、守る場合には分を辨え、争いに際しては正々堂々と義をもって立ち向かい、礼を失する様な打ち方はせず、形勢判断にあっては智をもって的確に処置している。
碁とはそういうものであるから、月並みな他の遊芸と同じく単純なる閑つぶしの道具と見なしてよいものだろうか、と思うのである。
4
天暦(文宗帝の年号)の頃、私は帝の侍従として、学問所の師範役等を勤め奎章閣という所におった。文宗帝という人は政治の合い間を見ては遊芸場によく出入りした人で、中でも碁が好きだと見え、国の大官に命じて碁の名手を左右に侍らせ可愛がっていた。
ある時私に向かい、
「お前の家の虞愿という者は、その昔宗の微宗帝との話の中で、碁というものは君主たる者の好むものではない、と言ったそうであるが、本当にそういうものだろうか」と、お尋ねになられた。
5
そこで私は次の様にお答えした。
「古代の聖人が碁というものを作られてこのかた、碁に込められた精神やその意義の深さというものは、人の世にも通用し既にその真髄は極められたと申せましょう。決して無益な遊びどころではありません。
かの孔子さえも碁を打つ事は打たないより良い事である、と言っております。孟子も又、碁は数理を争うものであり、精神を統一し意志を強く持つものでなければ上達も覚束ない、と言っております。
まさに碁に言う布石や戦略、どう攻めるどう守るかという様な事は、国が政令を施行する時機のつかみ方や軍事行動をとる場合の作戦と似ており、碁を習うという事は、とりも直さず平安な世にあっても乱世に処する志を常に忘れぬ戒めとなるものだ、と思います。」
山海堂 玄玄碁經 より抜粋 |